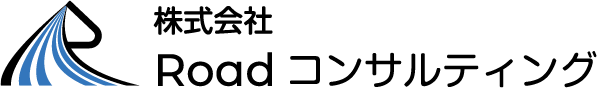令和7年度静岡市地域包括ケア研修レポート「カスタマーハラスメントから職場や自分を守る」
2025年10月21日に静岡市主催の令和7年度 静岡市地域包括ケア研修を担当させて頂きました。
テーマは、多くの職場で関心が高まっているカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)で、静岡市の地域包括支援センター等で働く40名程度の職員様に参加して頂きました。
依頼をしてくださった静岡市の担当者様が熱心な方で、事前に研修の内容や進め方等に関する相談をさせて頂きました。
その中で、福祉の現場でカスタマーハラスメントに悩む職員は多く、その予防や対策は簡単ではないことを確認させて頂きました。 そのため、本研修では、カスハラの定義や国が推奨する予防・対策の方法等の基礎知識を学んだ後に、施設ごとにカスハラが起こってしまう要因を分析し、実践的な対策を考えるワークを実施しました。

研修の見出し
- カスハラの概念誕生の経緯
- カスハラの定義(社会通念上許容される範囲を超えた言動とは)
- 具体的なカスハラ被害の実態
- 事業者における措置義務の方向性
- カスハラ対策チェックシート【ワーク】
- 福祉現場におけるカスハラの実態
- 福祉の現場でハラスメントが起こってしまう要因を考える【ワーク】
- カスハラ発生時の対応を検討する際の視点と対応例
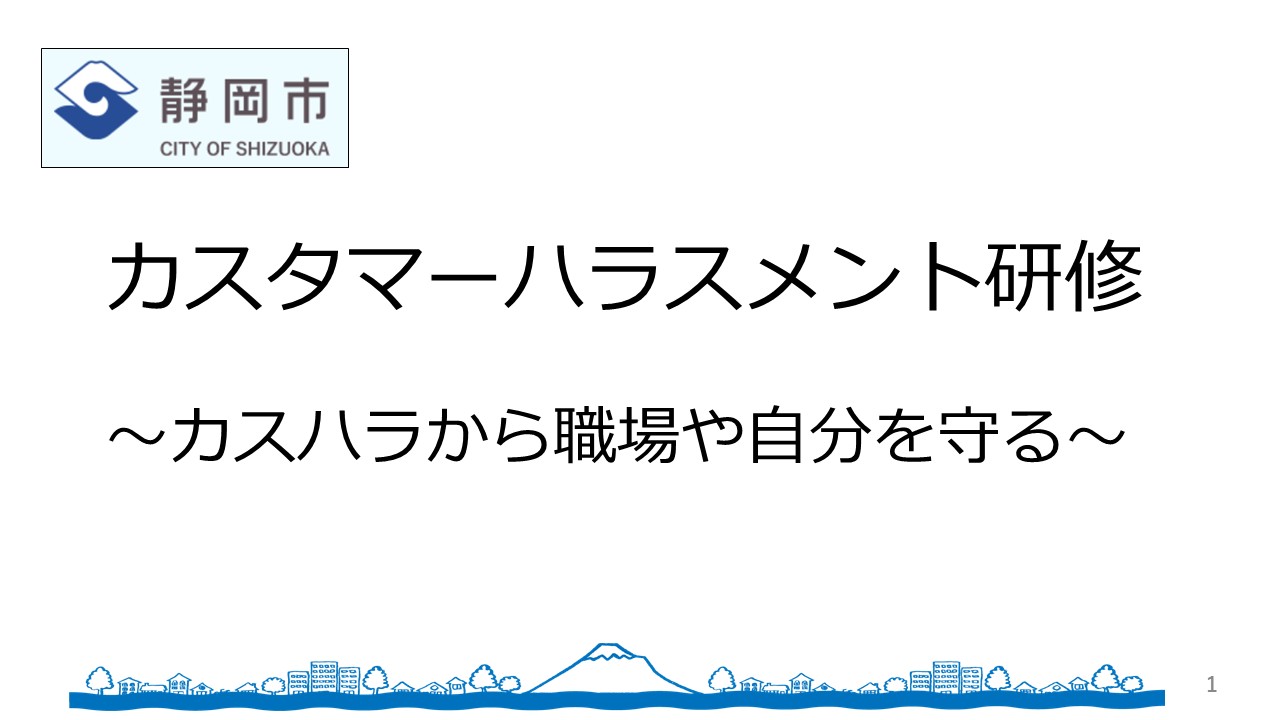
おわりに
今回の研修を通して、現場で奮闘される職員様の様々な声を聞くことができました。
その中で、カスハラは他のハラスメントとは異なり、顧客等が相手なので、どれだけ予防策を講じたとしても発生してしまう可能性があることを再認識しました。
そして、カスハラは、顧客と担当した職員との間の問題として扱われがちですが、担当職員は会社の中で役割を担っているに過ぎません。会社や職場がそのことをどれだけ理解し、担当職員をサポートできるかがポイントになります。
そのため、私は職場の団結力を高めることこそ、本質的なカスハラ対策だと考えています。
福祉の現場におけるカスハラは、利用者や家族が相手になるため、デリケートであり、時間をかけた辛抱強い対応が求められるケースが多いです。
そのような時に、職員同士が信頼関係で結ばれたチームになっていれば、担当職員を孤立させることなく、チームで連携し、マニュアル等に基づき、粘り強く対応することができます。
一方で、職員が自分勝手で、仲間への思いやりに欠けた職場であったとしたら、担当職員の負担は重くなり、事態は深刻化してしまうと考えるからです。
信頼で結ばれた職場をつくることは、カスハラに限らず、クレームやトラブル等、あらゆる課題に対応する上でも効果的です。
今回の研修現場を通して、改めて職場づくりの重要性を確認させて頂きました。このような機会を頂き感謝いたします。
大道 和哉